毎年の交野平和展で、戦争体験を綴った、聞き取り手記集”先輩からの伝言”を発行しています。今年も、四名の方から協力を得て発行を予定にしています。その中の一人、寺田露子さんの「私の戦中・戦後の体験」を交野革新懇ニュースに掲載します。
天野が原町 寺田露子(98歳)
私は昭和2年、東成区今里で2人姉妹の長女として生まれました。
鶴橋第3小学校に入学しました。小学校卒業後境川女子商業を受験、合格。路面電車で通学しました。学校ではほとんど勉強はなく奉仕活動が多かったです。梅田で千人針を頼んでしてもらったり、戦地の兵隊さんへの慰問袋をつくったり、軍需工場での奉仕活動をしていました。三国の昭和アルミの工場で飛行機のプロペラの部品を磨いていました。お国のためと思ったので苦労ではありませんでした。防空壕は地面に穴を掘って上に畳をかぶせたようなものでした。
昭和20年くりあげ卒業。戦争の中での学校生活でした。このような中でも友達と歩いて京都まで行き、嵯峨野の竹林を見てきれいと話す楽しさもありました。
18、19歳の傷つきやすい年ごろでした。
その後、女子挺身隊に所属しました。働ける人が少なくなっていたので、いろいろな仕事の女の方がいました。軍需工場への仕事が多かったです。電車に乗って移動中に車掌さんが、「空襲警報」というと、乗客はみんな降りて、草原や溝に隠れました。草原にウサギを打つような飛行機からの機銃掃射がありました。そのあと、打たれて亡くなっている人もいましたが、そのまま電車は動き出しました。このようなことが日常だったので怖いと思いませんでした。
別の女子挺身隊に所属していた友達は、森ノ宮の陸軍砲兵工廠が爆撃されたとき死亡したと聞きました。物資はなく親は大変だったと思います。食料は配給制で甘いものはなく、お菓子屋の娘にうまれたかったと友達といっていました。麦ごはん1日3合、固形醤油で味付けしたものでした。みんな同じでした。薪がなくなり本を破いてご飯を炊きました。
大阪空襲
3月13日に家が焼け、熊取の母の実家に荷物を荷車に積んでいきました。納屋を借りて住んでいました。
終戦の日(8月15日)の天皇の話は、疎開していた家で聞きました。ゆっくり寝られると思ったのでうれしかったです。
戦後は必死でした。声をかけてくれる人がいて、村役場に手伝いに行きました。田舎でしたので、食料は手に入りました。なんばきびの配給があり、それをパン屋にもっていき、パンと交換してもらっていました。戦争でなければ、おしゃれをして楽しい青春だったと思いますが、みんな同じです。時代がそうでした。
女の人は戦死でなく爆死だ。と思います。先生は神様と思っていました。なぜ、本当のことを教えてくれなかったのかと、今も思います。
結婚をして子育てに忙しかった時期が落ち着いて、本を読みいろいろなことを知りました。シンガポールや沖縄に行きました。沖縄にいきましたのは、同じ時代を生きたものとして私もひめゆりになっていたと思い、身代わりで行ってきました。
夫も戦争に行って、帰ってきた人でしたがその体験はあまり語らず、胸に思うものはいっぱいあったと思います。夫の死後、聞いてやればよかったのではと、後悔があります。
(2025年6月聞きとり) 久保隆枝

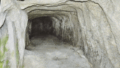

コメント