カンアオイ 天野が原 久保俊雄
森林内に生育するウマノスズクサ科の常緑多年草です。交野では倉治、源氏の滝から交野山への登り道右側と傍示周辺で見られます。
二本の葉柄の先にハート形の葉をつけ、その根元に先端かが3つに裂けた小さく堅い筒状の花(萼筒)を咲かせます。花弁は退化しており、暗紫褐色の地味な花を晩秋から冬にかけ地表すれすれに咲かせます。花は春先までほぼそのままの姿で残ります。
花が咲き終わると新しい葉が伸びて古い葉と交代します。初夏にはすでに新芽の形成が始まっており、夏の終わりには小さな花弁ができ、秋には蕾出して萼筒を開きます。地下では、棒状の堅い根茎が短く這い、脇芽をつくつてゆっくりふえていきます。

日本各地に分布していますが、地域による変異が多くあり、葉の班入り模様や花の形・色の変化が多く見られます。成長が非常に遅い植物で、人里に比較的近い里山に多く生育するため開発やマニアの乱獲で激減しているのが現状です。
一方、古典園芸植物として、葉の班入り模様や花の形や色の変化に注目した交配が行なわれ、いろいろ特徴ある品種が作出されてもいます。種の保存の意味からも好ましいのではないでしょうか。


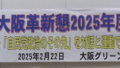
コメント